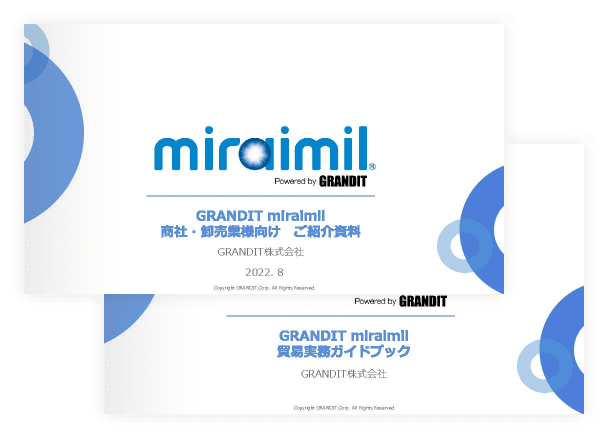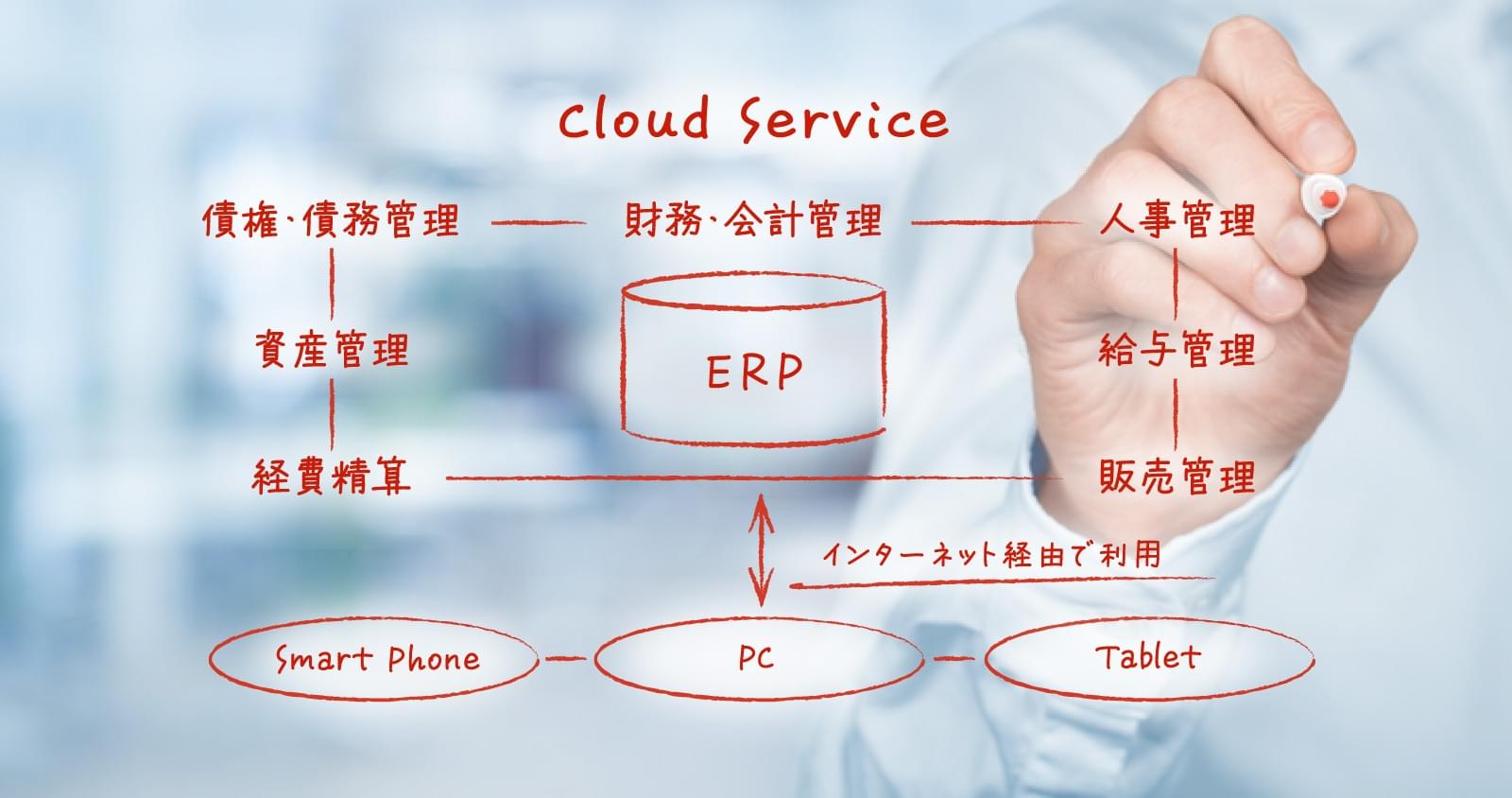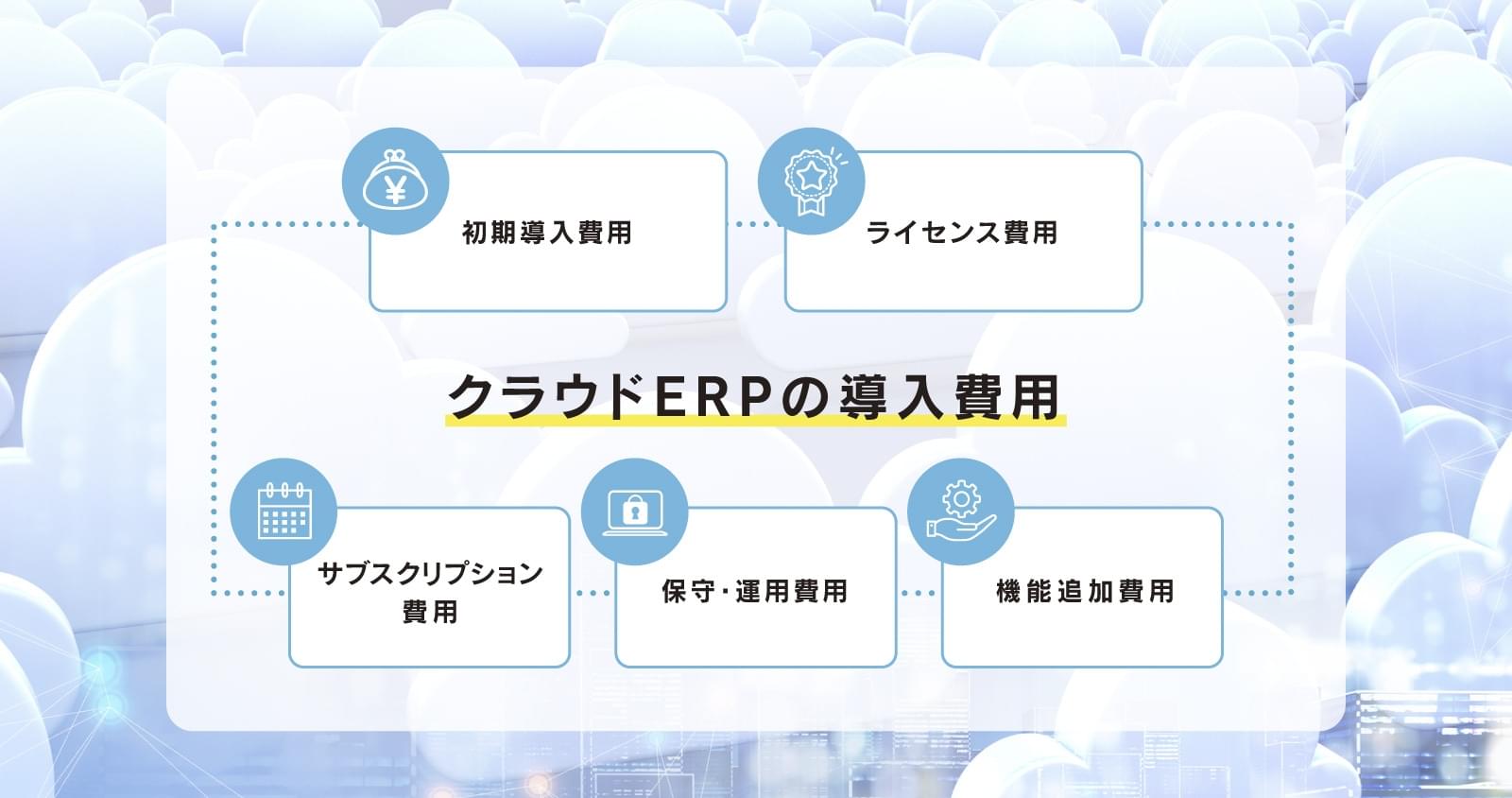輸入貿易の基本を5WIHの視点から解説します!

輸入プロセスについてはモノの流れ、カネの流れ、書類の流れがあります。このコラムではコンテナ船を利用した輸入のモノの流れにフォーカスし、本邦(日本)に到着後、外国貨物が輸入通関をへて内国貨物に至るまでについて説明します。
目次
輸入プロセスのWhen:時間について
コンテナ船を利用した、一般的な海上輸送の輸入のプロセスは以下のようになります。ここでは各々の工程で必要となる所要時間について説明します。
- 現地から輸出
- コンテナ船(本船)で外国貨物を海上輸送
- 本船が本邦に到着
- 外国貨物を保税地域に搬入
- 税関へ輸入(納税)申告
- 審査、検査を受けて輸入許可
- 内国貨物として国内引き取り
1.現地から輸出についてかかる時間は、輸出国の税関検査、輸出許可の状況によって異なります。現地の状況に関する相談は、日本貿易振興機構(JETRO:ジェトロ)の貿易投資の窓口にされるとよいでしょう。JETROは各都道府県に1か所(長野県と福岡県は2か所)の窓口があります。またJETROは海外の各国にも事務所がありますが、現地事務所への相談は当該国以外からは受け付けていないのでご注意ください。
例えば、中華人民共和国の場合、現地のCIQ(入境検験検疫局、日本の検疫所に相当)における輸出前の検査に長期間を要する場合があります。そのため本邦到着までのリードタイムの見極めが困難な場合があります。
2.のコンテナ船を利用した海上輸送について、輸出国から本邦までの所要日数ですが、輸出国から本邦への距離と経由地によって異なります。例えばアジア圏の以下の都市から輸入した場合、下記の所要日数がかかります。
- 中華人民共和国の上海→東京 3日
- ベトナム社会主義共和国のホーチミン→東京 7日〜13日
コンテナ船の所要日数を調べるには「Freightors」というサイトがあります。このサイトでは海上便と航空便の所要日数を調べることができます。
一方、本邦到着までの所要日数は、外部環境の影響を大きく受けることがあります。例えば、コロナウイルスの世界的蔓延や米中貿易摩擦の影響で、2020年11月以降、多くの地域で港湾の混雑、コンテナ船の沖待ち、コンテナの不足などによる大幅な輸送遅延が続きました。特に米国西海岸の港湾混雑は悪化し、コンテナ船が着岸するまで1週間、荷役に1週間と通常時の2倍〜2.5倍以上の日数を要する状況も発生しました。その結果、本邦への輸入においても輸送遅延が発生しました。(2022年9月現在、遅延は解消傾向に向かっています)
3.〜7.までの本邦到着後の所要時間については、輸入通関の一連の手続きとなるため、まとめて記載します。本船到着後、外国貨物は原則としてまず貨物を保税地域に搬入されます。その後、輸入(納税)申告をして必要に応じ、税関の審査や検査を受け、税関の輸入許可書取得後に内国貨物として国内に引き取ります。
一般貨物のNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System:輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用した、本船入港(日本到着)から輸入許可までの輸入手続き全体に要する平均所要時間は、2.5日(59.5時間)となっています。(財務省関税局「輸入手続きの所要時間調査第11回」2015年3月実施)。
そのうち、輸入申告から輸入許可までの通関の所要時間は2.4時間となっています。通常は輸入申告の当日中に輸入許可が下ります。ただし申告した時間帯が夕方の場合、翌日の許可となります。なお、税関の現物検査、モニタリング検査が行われる場合や、他法令の許認可審査などに時間がかかった場合は輸入許可まで、さらに時間がかかる場合があります。
注意すべき点があります。それはフリータイムです。
フリータイムとは本船から陸揚げされたコンテナが、コンテナヤード(CY:Container Yard)からの搬出されるまでの「無料保管期間」のことです。または、CYからコンテナを引き取り、コンテナ保管場(Van Pool)へコンテナが返却されるまでの「無料貸出期間」をさします。フリータイムは利用する航路や船会社等で異なります。コンテナの所有者は船会社や物流輸送専門会社、リース専門会社のため、返却する必要があります。
フリータイムを超過すると「デマレージ」が発生してしまいます。デマレージとはコンテナの「超過保管料」のことです。陸揚げされたコンテナがフリータイムを過ぎてもCYに引き続き留置された場合に課せられます。そのため、フリータイムの期間内にCYからコンテナを搬出し、荷受人に貨物を納品しコンテナを返却しなくてはなりません。
なお、フリータイムの日数、デマレージの計算ルールと金額は利用する船会社ごとに異なりますので、船会社へ確認してください。
輸入プロセスのWhere:関わる場所について
輸入のプロセスに関わる場所については、コンテナが本邦到着後の場所について記します。
本邦到着後、輸入港で陸揚げされたコンテナは、保税地域に搬入されます。保税地域とは輸入許可がおりる前の外国貨物が搬入され、蔵置される場所の総称です。保税地域は税関の管轄下にあります。関税法第30条では「外国貨物は原則として保税地域以外に置くことはできない」と定められています。
コンテナで輸入される貨物にはFCL貨物とLCL貨物があり、それぞれ荷揚げ後の搬入先が異なります。
FCL貨物とLCL貨物の違いは以下になります。
- FCL貨物:一荷主だけの貨物で1本のコンテナを満たす大口貨物で、搬入先はCY(コンテナ・ヤード)です。
- LCL貨物:複数の荷主の貨物で1本のコンテナを満たす小口貨物で、搬入先はCFS(コンテナ・フレイト・ステーション)です。
いずれも輸入通関手続きを行い、輸入許可後に貨物を引き取りますが、各々引き取り形態が異なります。
FCL貨物は一荷主だけの貨物のため、コンテナごと引き取ります。一方、LCL貨物はコンテナ・フレイト・ステーションで、荷主ごとに仕分けされますので、貨物の現物を引き取ります。
輸入プロセスのWho:輸入に関わるヒト
輸入のプロセスにはさまざまなステークホルダー、いわゆるヒトが関わります。モノの観点からは船会社と海貨業者が大きく関わってきます。
船会社は荷主から船腹予約(スペースブッキング)を受け貨物を目的地に運ぶ役割を担います。
一方、コンテナで輸入を行う場合、荷主と接点が多いのが海貨業者になります。海貨業者は荷主に代わり、船会社に対する船積みや荷受に関する手続きを代行します。「乙仲」とも呼ばれますが、これは旧海運組合法で、乙種海運仲立ち業と呼ばれていたことに由来します。
海貨業者の多くは税関長から通関業の許可も受けています。そのため、輸入(納税)申告や関税、消費税の納付などの対税関手続きなど各種手続きを代行することができます。また、倉庫や輸送手段を保有する場合は、輸入後の貨物の蔵置、仕向地への輸送なども合わせたプロセスを、一気通貫におこなうことが可能です。
海貨業者は荷主と船会社を結びつけ、通関手続、税関への納税手続きや貨物の管理など、輸入に関わる手続きをワンストップで代行してくれます。
輸入プロセスのWhat:税関の役割について
輸入のプロセスの中で、極めて大切な役割を果たすのが税関です。税関の輸入許可なくして、貨物を輸入することはできません。輸入許可がないものは密輸品となります。税関は財務省の管轄下で、貿易取引の要として存在します。税関の役割として主に以下が挙げられます。
1. 貨物の通関
輸出のみならず輸入において、その旨を税関に申告すると税関はこれを審査し、輸出(輸入)許可を与えます。
輸入時においては輸入申告に基づき、関税、消費税の徴収をおこないます。また、免税が可能な申告に対しては免税の措置をおこないます。
関税の決定のベースとなるのが、実行関税率表です。これは「HSコード」というHS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)の品目番号に従い、作成されています。HSコードとは国際貿易の円滑化をはかるためにWCO(世界税関機構、本部:ブリュッセル〈ベルギー〉)によって定められた貿易のための共通な品目番号です。
2. 関税、消費税などの租税の徴収
輸入によって発生する税金を徴収したり、免税をおこないます。
3. 密輸の取り締まり
輸出、輸入が禁止されている貨物の取り締まりをおこないます。
4. 保税地域の管理
外国貨物が輸入許可を得るまでの一定期間、蔵置されるのが保税地域です。税関はこの保税地域の管理や取り締まりを行います。
輸入プロセスのWhy:なぜその役割をおこなうのか
税関が前述の役割を担うには理由があります。適正で健全な輸出入を保つ必要があるためです。関税制度を設けることで、国内産業の保護を目的としています。海外製品と国内製品の価格を比較したとき、消費者が関税分が安い国内製品を購入するようにできるようにする為です。
輸入プロセスのHow:税関の役割に対してどのように対応するか
税関が輸入許可を出さない限り、外国貨物を本邦に輸入することができません。法令上、輸入する貨物がそもそも輸入できるモノであるか確認し、輸入の許可が必要なものであれば、事前に必要な許可などを取得しておく必要があります。ここに記載している輸入許可は通関時に関税、消費税を納付後に下りる許可とは異なります。法的規制上問題がないか、輸入する貨物が日本国内に持ち込まれる事に対する許可になります。貨物によっては外国為替および外国貿易法(外為法)の規定によって経済産業大臣の輸入割当、輸入承認が必要になる場合があります。加えて、外為法以外の法令によって、貨物を所管する大臣の輸入許可が必要な場合があります。従ってこれらの輸入割当、輸入割当や輸入承認、所管官庁からの許可は輸入通関の前に入手しておく必要があります。
【参考文献】
- 片山立志『よくわかる貿易実務入門』(日本能率協会マネジメントセンター、2022年)
- 蘇我しのぶ『貿易実務の基礎がよくわかる本』(C&R研究所、2020年)
- 片山立志『絵でみる貿易のしくみ』(日本能率協会マネジメントセンター、2020年)
- 高橋靖治『貿易のしくみと実務』(同文舘出版、2015年)
【参考URL】
- コンテナ船の所要日数確認サイト「Freightors」
https://www.freightos.com - 日通ロジスティクス用語辞典
https://www.nittsu.co.jp/support/words/abc/customs-immigration-quarantine.html - 国土交通省 コンテナ不足問題に関する政府における取り組み
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001403345.pdf - JETRO 輸入貨物の到着から引き取りまでの手続き
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010136.html - 東京検疫所 食品管理課 食品等輸入届出の手続きの流れ
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a003.html